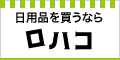皆さん、こんにちは。^^
「介護サービスを受けるには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。」
【介護認定の簡単な流れ】
- 市の担当窓口等で、介護認定手続きの申請をする。
- 調査員の方が家に来て、本人や家族からの聞き取り調査をする。
- 全国共通の調査票を元に、本人の状態を判断する74項目の調査が行われます。
- 一次判定:調査票の結果は主治医と共にコンピューター処理されて、どのぐらいの介護が必要なのかの指標とされます。
- 二次判定:要介護認定等申請に基づく認定調査の一次判定結果及び特記事項、主治医の意見書により、対象者の介護の必要度の審査判定が行われます。
- 要介護度の認定結果が決まります。
要介護度の判定がされた後に、担当のケアマネジャーがひと月ごとに作成するケアプラン(介護計画書)に沿って、日々の介護サービスを受けれる事になります。
今回は、簡単な介護認定についての知識と体験談等を踏まえて記事にしてみました。
【介護認定に立ち会う事に】

先日、ご高齢のお得意様から介護認定を受ける手続きがあるので同席して欲しいと頼まれました。
自分が父の長い在宅介護経験があること、父の介護認定を3回程経験してること、お客様にお子さんが居ないことや親族が離れて暮らしてるということでお願いされました。
第三者の他人でも、同席して一緒に手続きを進めるのは可能だそうです。
約20年来のお付き合いをさせて頂いてるお客様なので、お元気な頃から最近までの状況はある程度解ってるつもりなので、その範囲ないでお手伝いしようと思います。
介護認定を受ける本人だけでは手続きは、基本的には難しいと思います。
- 出来る事を出来ないと言ってしまったり
- 出来ない事も出来ると強がってしまったり
現在の状況を正しく申告しておかないと、介護判定に影響してしまうので
とても重要な作業になります。
【要介護・要支援って何?】

ある程度、高齢のご家族が居られる家庭なら「要介護・要支援」という言葉は一度は聞いた事がある言葉だと思います。
◎要支援って?
要支援とは、日常生活の上で基本動作については問題なく自分で行う事ができるが、多少の支援が必要な状態のことです。
◎要介護って?
要介護とは、日常生活全般において、自分だけで行う事が難しく、誰かの介護必要な状態のことです。
お風呂やトイレが1人ではうまく出来ないなどの、具体的な生活支援が必要な状況です。
広告
◎介護認定は7段階に分けられている
介護認定には、要支援1~2、要介護1~5の7段階で判定されます。

それぞれの段階で、介護保健支給限度額が異なります。

◎介護保険の支給限度額はどれぐらい?
自己負担分で支払うのは、本人の合計所得が160万未満の場合は1割負担、それ以上の所得がある場合は、所得に応じて2割、3割となります。

支給限度額を超えてしまった分は、全額自己負担となってしまうので注意が必要ですが、その辺は担当のケアマネジャーがケアプランできちんと管理してくれるはずです。
◎注意点!
注意すべきは要介護度認定が、本来の状態よりも低く認定されてしまうと、使いたい分の支給限度も低く設定されてしまう為に経済的にも苦しくなってしまう可能性がでてきます。
介護保健を使って、必要な介護サービスを受けたいのに介護認定が実際より低い為支給限度額がすぐにいっぱいになって保険適用で使えなくなります。
どうしてもサービスを受ける必要がある場合は、全額自己負担となってしまい大変です。
◎介護認定度によって受けれるサービスが違う
それぞれの介護認定された段階によって、受けられるサービスが違ってきます。
- 在宅で受けれるサービス
- 施設等で受けられるサービス
受けられるサービスの詳細は、担当になったケアマネージャーの方から聞いて頂くのが間違いないと思います。
介護される本人の状態や希望によっても、サービス内容や組み合わせも変わります。
- 要支援 ➡ 重い介護状態にならない事を目的とした、介護サービスを利用します。
- 要介護 ➡ 介護サービスを受けながら、さらに状況が悪化しないことや、現状維持もしくわ改善を目指す為の介護サービスを利用します。
【実例:父の介護サービス利用】

うちの父は在宅で約16年間の介護が続きましたが、初期の在宅介護の頃は要介護2で、在宅介護終盤~施設に入所した時は要介護4でした。
介護の重さも上から2番目だったので、かなりの介護サービスを利用していたと思います。
- 週3回のデイサービス
- 週1回の訪問リハビリサービス
- 電動昇降椅子のレンタル
- 車椅子のレンタル
- 不定期の訪問歯科診療サービス
- 不定期のショートステイ(お泊り)サービス
介護保険のサービスなしでは、とうてい父の在宅介護は続ける事はできませんでした。
もちろん施設入所中の現在も、介護保険の利用は継続中です。
広告
【お客様の介護認定の立ち合いを終えて】
認定に来られたは、市の担当の課の方1人でした。
決められた項目を、ご本人に直接聞きながらチェックして進めていき1時間もかからずに終わりました。
確認の必要等がある時だけ、自分に話かけるという感じです。
面談が始る前に、「聞かれた事に正直に答えるようにして下さいね。」と声掛けをしましたが、ケアマネさんから少しオーバー目に言っても大丈夫と言われていたようです。
◎結果は数週間後に郵送で届く
介護認定は、その場ですぐに判断されるものではありません。
今回のご本人の面談は立ち合い人の話も含めて、作られた書類を元にして後に主治医や専門の機関などの見解を踏まえて判断されることになります。
◎お客様はどうだったのか?

もちろん正式な判定はまだ出ていませんが、個人的な見解として書きます。
恐らく今回は、介護認定されたとしても一番軽い要支援1または要支援2かなと思いました。もしくは判定外の自立か。
判定員の方の質問には、率直に答えてられましたし強がって嘘などもついていませんでした。
結論的に言うと、ここ最近の急な体調不良などがあるものの要支援・要介護の状態ではないかなと言う感じです。
判定員の方も、質問等にもはっきりと答える事ができますし、身体的なチェック等も比較的スムーズに行えました。
認知機能的な点も、ご高齢な事を考慮しても現時点では問題ないように思います。
介護保険でサービスを受けるとなると、介護認定はとても大きな役割になりますが、今回はあまり期待できないかなと思いました。※期待するものでもありませんが。
主治医の先生がつい最近変わってしまったこともあって、お客様の身体や体調の事を詳しく解ってなかったのも、今回のような展開になった原因かもしれません。
【あとがき】
今回は簡単にですが、要支援・要介護についてまとめてみました。
実際のところは、担当されるケアマネージャーやご家族でしっかり相談する事が大事だと思います。
ご家族の介護を始める為には、まず介護認定からと言うお話でした。

介護をサービスを受けると言うことは、人と人との付き合いになります。
ケアマネさん、リハビリの先生、看護師さん、介護士さん、市の担当の人、その他関係者の方々、当然人それぞれで性格も考え方も仕事のやり方も動き方も皆さん違います。
人との出会いタイミングもあれば、施設を利用するタイミングもあります、人同士の相性も大きく関係してきます。
介護サービスを利用するという事は、ただ身の回りの世話などをお願いするだけではないという事を長年の在宅介護で嫌と言うほど体験してきました。
その他にも、いろいろな悩みも問題も次から次へと出てきます。
そんな事もあるので、ご家族がお元気なうちから介護についての知識や情報を少しずつでも集めて共有しておいた方が良いのかなと思いこのブログで発信しています。
少しでも、何かのお役に立てればと思います。^^
?